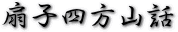
扇子
皆さん、「扇子」と聞いてどんな種類を連想されるでしょうか?
まず、夏場に涼をとろうと風をおこすために使う「夏扇子」。
次に日本舞踊や舞台で使用される「舞扇子」、それから結婚式で留袖を着たときに手に持つ「6寸金銀」のように冠婚葬祭の儀式に用いられる「祝儀扇」ではないでしょうか。その他にも茶道の際の「茶扇」や「飾扇子」など結構種類は
多いのです。
ではその扇子の発祥地は?・・・中国かな?と思いの方もいらっしゃるでしょうが、答えは日本です。平安時代に京都で生まれたと伝えられています。その起源においては、紙の代わりに長細い「木簡」を閉じ合わせたものでありましたが、その後紙や竹を主材料とした現在も使われている形へと発展してきました。
後に、中国でも同様の材料でもっと簡素な扇子が作られ始めました。
でもここ数年は、日本への輸出目的で安価な商品が入り始めて、古くからの職人さんの仕事が減ってきているのが現状です。衣類やタオルと同じです。
ヨーロッパでも主にスペインで作られているようです。装飾や踊り用のようです。
何年か前にディスコ全盛時に、ボディコンのお姉さんがヒラヒラの房がついた扇子を持って踊っていたのを覚えている方もいらっしゃると思います。それと形は似ていますね。異論がある方は情報をお寄せください。
日本で扇子を製造している業者は、やはり京都に一番多いようです。そして職人さんも。その他、大阪、名古屋、東京でも製造されています。
京都にはお寺の総本山などが多いので、お坊さんが持つ「中啓(ちゅうけい)」と呼ばれる扇子を専門に製造している業者もあります。
「ファンティーク」では、広く、多くの方にご使用されている「夏扇子」と「飾扇子」を扱っています。
ご自分でご使用いただくも良し、大事な方にプレゼントされるのもよろしいかと思います。
また "日本に1本しかない自分のオリジナルを作ってみたい" という方のご要望にもお答えしております。一度ゆっくりとラインナップをご覧ください。
|